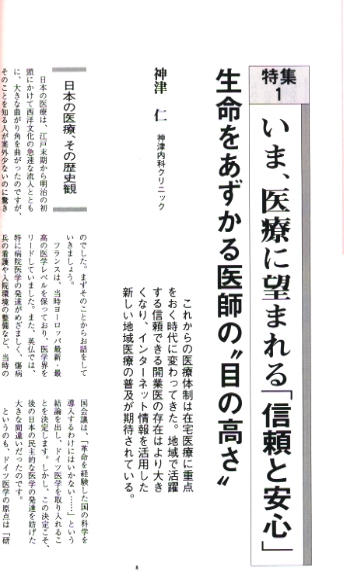
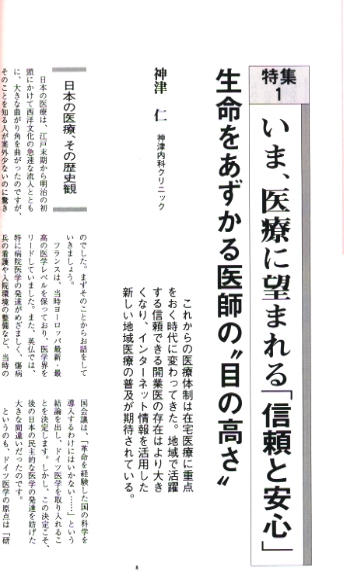
ここ一、二年の間、毎日の新聞やテレビに頻繁に登場するので、「インターネット」という言葉は、もう日本語になってしまった感があります。空間的な距離をおいて、各地で使われているコンピューターを、電話回線で結び、共通のコンピューター言語で情報の受け渡しを行う方法がこれですが、この方法は次第に進歩し、最初は文字情報のみだったものが、最近では静止画像や動画まで送れるようになりました。しかも、地球を一秒間で7回り半する光の速度で行われますから、地球上のどんな場所からも瞬時にその情報が得られるという、すごい時代になったのです。
このネットワークは、アメリカの防衛戦略の一つとして、情報回線の網が一つ壊れても、他の回線を経由してまるで蜘蛛の巣を張り巡らせるように、構築されたネットワークが常に「生きている」ことによって、重要な情報網が寸断されないように考えられて作られたものでした。しかし、この情報網は、冷戦終了後の世界においては、戦争を想定した戦略的手段より、学術研究者の情報交換の道具として次第に用いられるようになり、ソフトウェアーの飛躍的な進歩とともに、医療情報発信ツールとして大いに用いられるようになったのです。
医療情報は、文字、図、表、写真、あるいは心電図などの生体記録データ、レントゲン写真やMRIなどの画像診断情報など、その応用範囲が広範囲であることから、このネットワークを用いるのに非常に適したものと考えられました。また、日進月歩の昨今の医学情報を得ることによって、遠く離れていても診療そのもののレベルを世界と同等のものに引き上げることが出来ますし、遠隔地にいても他施設の専門家の意見を聞くことが出来るといった多くのメリットが存在するので、医療関係者は非常な興味をもって参入し、多くの情報を発信し始めたのです。最近では、「狂牛病」や「O−157」といった情報が、今までの何十倍といったスピードでインターネット上で情報蓄積され、公開されていったことは記憶に新しいところです。と同時に、医師や看護婦のいる所に出かけていかなければそうした情報が得られなかった時代から、一気に自分のコンピューターでそうした医療情報が得られ、しかも一流の臨床医や専門医の意見を直接聞くことが出来る時代に入ってしまったのです。ただし、入ってくる情報は、それが正しいという特別な裏付けがあるわけではないので、それが信ずべき情報ソースであるかどうか、自分自身でしっかり見極める必要が出てきました。
前項で述べたように、近代日本の医学教育は、ドイツ式で始まり、アメリカ式にシフトしたのですが、教育機関の官僚主義、権威主義は変わりませんでした。ここにインターン闘争や東大紛争の起源があるといわれています。医学部の大きな目的は、「医師の養成」です。戦前は医学部を卒業すれば、そのまま医師になれました。現在のフランスも同様ですが、医師国家試験などというものはありませんでした。私は、日本の国は、民主主義ならぬ「免許主義」だと思っていますが、国家のお墨付きがなければ何事ともまかりならんという国のようです。平成の御世でも江戸時代と一緒で、様々な「関所」を作って人々を管理するということを連綿として続けているのが我が国のやり方です。欧米では、地域間の基幹道路はフリーウェイといって殆ど無料で通行ができ、国が責任をもって管理・運営しているのが普通です。日本のように短い距離で料金所を設けて、しかもその料金をいつまでも値上げし(天下り官僚の退職金配給機関になっている首都高速道路公団なる不思議な機関を作って)、非難されないという政府は珍しいのではないでしょうか。
話は変わりますが、私がアメリカにいた時、夏休みで家族を連れて英国領バージン諸島に行ったときのことです。私は大学時代からヨットを生涯スポーツとして楽しんでいるのですが、この時はセントトーマス島で40ftのセーリングクルーザーを借りることにしたのです。日本では、小型船舶免許というものがあって、それがないとエンジン付の船には乗れないことになっています。私もその一つを持っているのですが、しかし、セントトーマス島で船を借りるときに必要だったのは、どんな船にどれくらいの期間乗っていたか、という「実地経験」であって、免許の有る無しではなかったのです。考えてみれは、当然のことでしょう。1000万円以上する豪華ヨットを、「免許」があるというだけで、何が起こるか分からない海という自然の中、経験の乏しい見ず知らずの他人に貸すなどというリスクを冒すはずがありません。つまり、欧米では「経験」がまず問われ、その経験に裏打ちされたものとしてのサーティフィケイト(証明書)が発行されているのに対して、日本で免許として発行許可する内容は、教育の最低レベルが示されているに過ぎないのです。こうした日本の状況で、医師を「医師免許を持っている者」として、社会が単純に割り切っているところに、大きな間違いが存在するのです。医師への報酬としての保険診療制度も、医師としての臨床経験を問わない設定になっており、大学を出たての医師も20年の経験を積んだ医師も、同じ金額が設定されているという事に、なんの疑問を感じないのは如何なものかと思います。勿論、国民はそこらへんの事情をよく承知していて、「評判の善し悪し」で医師を選びますから、外来が大変込み合う先生もいれば、そうでない先生も出てくるというわけです。
重ねていいますが、日本の医学部では、「良い臨床医になるためには」ということを教えなかったのです。それは、ドイツ医学の伝統である研究医学が中心であるため、「良い研究者になるため」の勉強は日夜やらされるのですが、患者さんを中心にした医療の大切さ、信頼される医師になるための心構え、などといったことは全く付録のようにしか取り上げられてはいないのです。学生を教える教授のほうも、良い臨床医だから選ばれるのではありません。つい最近まで、研究論文を積み上げて、その高さや重さで教授を選んだ時代が続いていたのです。ですから日本では、医学博士(Ph.D.)の方が臨床医(M.D.)より重んじられます。欧米の社会では医者でなくても医学博士はたくさんいて、理学部や生物学部や工学部出の研究者がPh.D.として医学部の教授になっていたり、研究室の研究助手でもPh.D.には比較的簡単になれたりします。しかし、臨床医(M.D.)になるためには、お金と時間をかけて得られた、かなりの知識と経験と、それに尊敬されるべき人格とが必要とされ、であるからこそ「M.D.」こそが彼らのステイタスなのだということを、私はアメリカにいて実感として感じました。ですから、研究論文の署名欄や名刺には、例え自分が研究や実験で得た成果からPh.D.をもらっていても、他のPh.D.のみの人達と混同されないように、必ずM.D.のみを掲げている、ということが分かったのです。日本では、「自分は医学博士である」と自慢する感覚がありますが、彼等にはないということが分かって、私自身ショックだったことがありました。つまり、社会的にも臨床医は医学博士の上にあるものだということなのです。しかし、考えてみればそれはそうです。実験をいくらやっても、ねずみや猫の心臓や膵臓が治せても、人間を診察・治療出来ない医師に、誰が診てもらおうと考えるでしょう。しかし、日本では、どこの大学でどんな研究をしたか、ということで「臨床医」の評価を下す(研究者についてはそれでいいのですが、臨床医はどんな指導医にどんな臨床指導を受け、どのくらいの数と種類の患者さんを、実際に自分でいかに診察し治療したか、という経験が、評価の対象にならなければおかしいはずです)勘違いを許す国です。本当は、そういう医師は研究所にいるのが相応しく、外来に出て来てはいけないのです。ところが、臨床医研修の最初から、そうした全く臨床医に相応しくない医学者に、診察の手ほどきを受けなければならない現状が日本の医学教育の実情であり、これを何とか変えていかなければ、第二、第三の薬害、医療過誤、そして患者側は知らないうちに学用患者(実験材料)にされてしまって、いつまでも患者中心の医療とは程遠い状況が続くという可能性があるのです。
生命をあずかる医師としての責任とその重大さは言うまでもありません。医の倫理について述べられた書物はたくさんあり、生命の尊さは比較するものがないと医師も考えています。しかし、医学の発達は、生命を救うこと、生命を維持する方向で進歩してきたため、救うことの出来ない命に対しては、極端に無関心であったり、無神経であったりする傾向が出てきました。大学病院の当直室で、「まだステら(死な)ないんだ、あのおじいちゃんヘルツ(心臓)だけは強いからなぁ・・・」という話をいやというほど聞いて、純粋で未熟な医師は育ちます。最新の医学をもってしても死に至る病はたくさんあるわけで、診断して治療して、うまくいかなかったら、次に救えそうな患者の方に興味が移り、あとはほったらかし、というのでは、子供が新しいオモチャに興ずるのと同じような心理だといわれても仕方ないでしょう。我々医師は、患者さんの病気を通して、導入部から死亡に至る、完結する人の一生に関わる医療を任されている、という意識を持たなければいけないのにもかかわらず、病院内の医療にあまりにも慣れ親しみすぎたため、死を家庭で、家族の見守る中で迎えるというやり方を、忘れてしまったようです。これが、大きな間違いであるということを、我々は大いに反省する必要があります。
最近では、ホスピスという概念が社会的にも受け入れられるようになり、生命の始まり(産科や小児科が関わる部分)だけでなく、命の終わりの部分に関しても、しっかりと関わることを宣言する医師が増えてきていることに安心を覚えます。しかし、医師が神の手に患者さんを委ねる一歩手前で、いかに振る舞うべきかは本当に大事なことであり、勝手な思い込みで「死そのもののプロセス」を歪めることのないよう、その重大さをしっかりと認識しながらこれに関わっていかなければならないと思います。そうした意味で、今後は「死の臨床」を研究し、若い医師たちに教えるシステムを作っていかなければならないと思います。
しかし、こうした考えも、多くは欧米の文化を踏襲したものであり、キリスト教的環境で進化してきたものであるので、今後は、日本の文化に出来るだけ適したものにしていく努力を我々は払わなければなりません。ガンの末期医療や、老衰の末期医療、それに直接関係の深い在宅医療、あるいは臓器移植の臨床的諸問題など、今後日本の医師が携わっていかなければならない部分は山積みにされているのです。
今まで述べてきたような、日本の医療の特殊な環境を、変えようとして努力している医師たちがいます。それが地域医療をあずかる若い開業医たちです。私もその一人ですが、恐らく、そうした医師たちに共通なのは、医師の目の高さだと思います。彼等は、ベッドの脇に腰をかけて、患者さんの目の高さに近づいて話をするでしょう。病気に関してはエキスパートですから、豊富な知識を皆さんに教えようとしますが、決して難しい医学用語を使ったりはしません。時に図を書いたり、図譜を見せたりして、出来る限り理解していただくように努力するでしょう。しかし、患者さんを甘やかすこともしないはずです。わがままな患者さんがいれば諭すでしょうし、たくさん待っている他の患者さんがいれば、その方達に迷惑をかけてまで一人に長い時間をかけることもないでしょう。しかし、次の診察のときにはきっと時間を割いてくれて、その患者さんが満足の行くように診療してくれるはずです。そして、知らないうちにうまくリードしてくれて、とても幸せな毎日を送らせてくれるはずです。高すぎもせず、低すぎもせず、信頼と安心を与えてくれる、そんな臨床医の目の高さを、我々も含めて日本の医療の目の高さにしていかなければならないと思います。