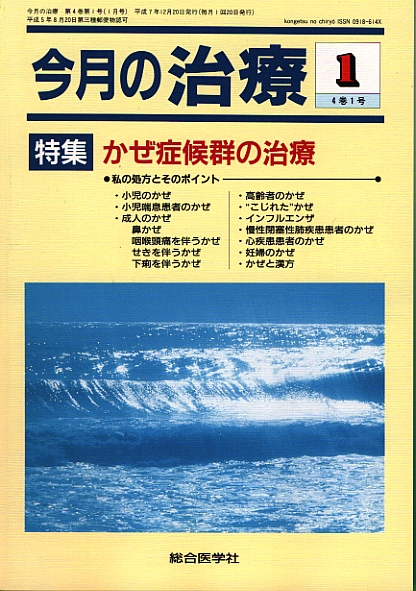
三冊の本
「三」という数字は、なんとも不思議な完成度を我々に感じさせる時がある。例えば、三種の神器、三国史、三冠王、三度目の正直、トリアス、等々、数え上げればきりがない。かつての旧制高校生は、デカンショなどと言って、デカルト、カント、ショーペンハウエルの三哲学者の書を読まずして青春を語れない、などと片肘張っていた。私も、ご他聞に漏れず、リルケ(詩人)、リスト(音楽家)、レマルク(医師で小説家)の三人に心酔していた時期があって、三の魔力を青春のエネルギーの高揚、発露に大いに利用したものであった。最近、グループ診療を研究する過程で、どうしても「メイヨーの医師たち(The doctors Mayo)」を読む必要があり、今まで久しくなかった、完結した「三」の手応えを強く感じたので、その話をさせていただきたい。
実は、名古屋の医学会総会で、大江健三郎氏の講演を聞いた時にも感じたのだが、恥ずかし気もなく、個人の理想や、宗教や、真理や、ためらいや、誠実さを語ることが、ひょっとすると今の日本人には特に必要なのではないだろうか、それを衒いもなく表出して一向に構わないのだ、ということを思ったのだ。特に、医師という人々は、これを一つの特性として持つことを許されていると。つまり、巷には、くだらない音や情報が氾濫し、ハレンチやら下品やらが罷り通っているが、我々の大脳皮質はそれに流されずにいて良いのだと、そして、病を癒す人として行動するためには、それこそが神から要求されていることなのだということを、これから紹介する三冊の本から改めて気付かされたからである。
「メイヨーの医師たち」(近代出版)は、ミネソタ大学が責任編集をした有名なメイヨークリニックの伝記であるが、それはまたアメリカの開業外科医と臨床医学の発展の歴史でもあった。この中には、教科書で良く名前を知っている医学者達がキラ星の如く出てきて、彼等の息使いまで聞えてくるような正確な描写に興奮を覚える。特に、研究医学を信条とするドイツの医学者や、頭の固い教授、新しい考え方に疑心暗鬼の当時のアメリカ医学会のおエラ方を論破する様子は痛快であるし、開拓時代の開業医(メイヨー兄弟の父親)の苦労を、日本における我々の先輩医師達の苦労に重ねてみると、いろいろな景色が見えて心が痛んだ。また、オスラー博士と偶然出会うシーンは、不思議な巡り合わせを感じさせる。もうお気づきと思うが、もう一冊は「平静の心(オスラー博士講演集)」(医学書院)である。病院での臨床実習を、初めて医学部の教育の一環として取り上げた内科医である博士の、主として多くの聴衆を相手に話された言葉を収録したものだが、臨床医としての心構えを(文学的表現を交えて)率直に述べていて、我々の心を打つ。三冊目は、「ヘッド・ファースト(希望の生命学)」(春秋社)。サタデー・レビュー誌の編集長であったノーマン・カズンズ氏が、UCLAの准教授として招かれ、いかにして患者の心の問題を、現代医学の中心的課題(精神神経免疫学)として捕えるようになったかを、非常に多くの具体的例を上げながら分かりやすく解説している。もともと難病を克服した氏が、病人として生きた経験から、いかに希望を持たせることが必要であるか、希望を失った人々がいかにして病に倒れていくか、それを次第に科学の目で解き明かし、アメリカの医学、あるいは医学教育が、いかに人々の自然治癒力をスポイルしているかを弾劾している。つまり、患者の目から見ると、今のアメリカの病院医学、医学部の学生教育や臨床研修(P60.インターンの期間の問題点)でさえ、いかに自己満足的で非人間的であるかを淡々と語っているのに驚かされるだろう。これを読むと、我々が感じている日本の医療や医学教育に対する疑問も当然であると、改めて考えさせられる。
このような訳で、今、私はこの三つの著書を、「臨床医を志す者の必読の三冊」に位置付けたいと思っている。そして、これらの本を、学生時代、研修医時代に読むことは、医学生としての自分あるいは医師としての自分が、歴史の中で、また社会の中でどんな座標軸の上にいるかを明確にすることでもあると思う。まだ若く、感性が鈍化していない、あなたに、是非とも読んでいただきたいと願うものである。
その他の文献
profileのページに戻ります。